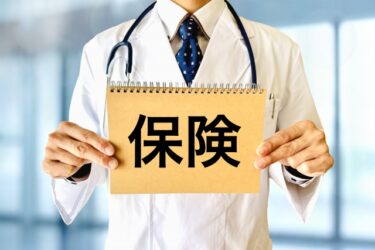アメリカや日本の代表的な会社の株をまとめたS&P500やTOPIXは、時価総額にもとづいて多くの会社の株をまとめたインデックスファンド(時価総額加重平均型)であり、市場全体の動きに連動するように作られ、手軽に分散投資できるので人気ですが、実は注意が必要です。

インデックスファンドのメリット
まずは、インデックスファンドのメリットを紹介します。
1. 大きな企業に重点を置いて投資できる
時価総額加重型インデックスファンドは、企業の時価総額(株価 × 発行株式数)が大きい企業により多く投資します。つまり、大きな企業が市場で成長していると、その分ファンドのパフォーマンスにも反映されやすくなります。大企業は安定していることが多いため、リスクを減らしながら投資ができるメリットがあります。
2. 個別企業の選定に悩む必要がない
インデックスファンドは特定の企業を選ぶ必要がないため、初心者でも簡単に投資できます。時価総額加重型インデックスファンドでは、自動的に時価総額が大きな企業に多く投資されるので、自分で株を選んだり、どの企業に投資するかを悩んだりする手間が省けます。
3. 変動リスクを分散できる
時価総額加重型インデックスファンドは、複数の企業に分散して投資するため、特定の企業が不調でも、他の企業や市場全体の動きでリスクを軽減できるという特徴があります。リスクを分散しながら、安定した成長を目指すことができるため、初心者にも安心です。
時価総額加重型インデックスファンドは、市場全体の動きに連動し、大企業に重点的に投資することで安定感と成長性を兼ね備えた投資方法です。選定が簡単で、リスク分散も効いているため、投資初心者でも手軽に始めやすく、安心して運用できるメリットがあります。
一見、便利なインデックスファンド。でも実は…、本質的な問題点を抱えている!
時価総額加重平均型インデックスファンドは、市場全体の動向を把握し、分散投資を行う上で有効な手段として広く利用されています。しかし、その仕組みには本質的な問題点が存在します。

1. 株式の本源的価値を考慮しない
時価総額加重平均型インデックスファンドは、企業の時価総額(株価 × 発行株式数)のみに基づいてポートフォリオを構成します。そのため、現在の株価が企業の本源的な “価値“ に対して割高なのか割安なのかを一切考慮しません。割高な銘柄が組み入れられる可能性が高まり、結果としてポートフォリオ全体の期待リターンを押し下げる要因となります。
2. 過去のパフォーマンスを過度に重視したポートフォリオ
時価総額加重平均型インデックスファンドは、過去に時価総額が大きくなった銘柄を過度に重視する傾向があります。過去のパフォーマンスが良かった銘柄が、将来も高いパフォーマンスを上げるとは限りません。むしろ、過去の成功に奢り、新たな成長機会を逃している可能性もあります。結果として、ポートフォリオが特定のセクターや銘柄に偏り、バランスの悪いものとなる可能性があります。
3. 将来の収益を考慮しない
時価総額加重平均型インデックスファンドは、現在の株価のみに焦点を当て、企業の将来の収益を考慮しません。将来の成長が期待できる企業でも、現在の株価が低ければポートフォリオへの組み入れ比率は低くなります。結果として、ポートフォリオが将来の成長を取り込む機会を逃してしまう可能性があります。
まとめ
時価総額加重平均型インデックスファンドは、手軽に分散投資を行える便利なツールですが、上記のような本質的な問題点を抱えています。
これらの点が、“集中投資の基礎(2)”で詳しく説明した、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイ社のリターンが、S&P500に比べて大きく上回る要因となります。
“企業の価値は、将来の収益によって決まること”、投資家の皆様は、このことを理解した上で、ご自身の投資目的やリスク許容度に合わせて、適切な投資判断を行う必要があります。
補足:
本稿は、投資に関する情報提供を目的としており、投資勧誘ではありません。投資判断は、ご自身の責任において行うようにしてください。